

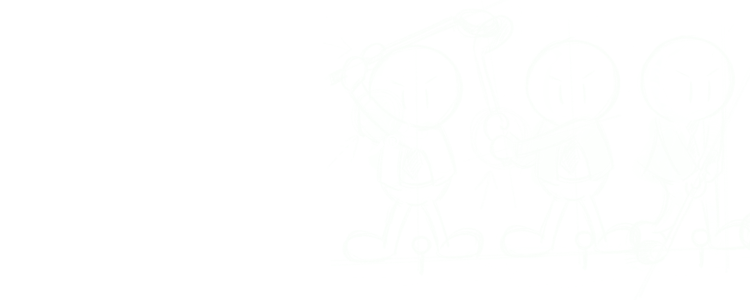
仕組みに必要不可欠なノウハウコミュニケーション®とは 後編
- 仕組みについてあれこれ
- 書籍紹介と実践解説
知識、技術など経験から培ってきた様々なノウハウを他者に伝えるということは、なかなか簡単なことではないですよね。
「ノウハウコミュニケーション®」についての後半。今回の大切なポイントは以下です。
形式知と暗黙知
他者とのコミュニケーションを今一度見直そう
形式知と暗黙知。ノウハウには2種類ある。
では、前編を読んで決意を固めたあなたに、事前にお伝えしておきます。
明文化には簡単には越えられないハードルがあります。
それは、ノウハウには形式知と暗黙知という2種類があるということです。
形式知
パソコンの操作方法や書類の記入方法、データ入力のやり方など、経験値が求められる割合は少なく、ある一定の決まり事の中で行われるノウハウが該当します。そのためマニュアル化しやすい種類のノウハウと言えます。
暗黙知
ハードルはこいつです。
営業スキルとか、調理とか、デザインとか、プレゼン力など、いわゆる匠の仕事に分類されるノウハウと言っても良いと思います。経験から培われたことや、感覚が求められ、言葉や文章で表すことが困難なノウハウのため、マニュアル化が困難です。

ですが諦めてはいけない。
感覚といえど何かしらの物差しがあります。五感を使い見定めている何かしらのポイントがあります。ルールに則った何かしらの順序があります。
経験から培った何かしらのルールを持っており、無意識にそのルールに従い再現性を高めています。
数値化しよう。基準になるポイントを探そう。
匠の仕事をよ~く観察してください。動画を撮る、録音するなどして分析してください。
そして徹底的にヒアリングしてください。
それを見つけて明文化することができたら、あとはそれを扱えるように鍛錬するだけです。二段目の「実践」ですね。
面白い事例があります。
ある割烹料理屋さんの厨房の中の話です。
調理の現場は職人技の現場です。多くの仕事に経験や感覚が求められる仕事だと思います。
しかしこちらの割烹料理屋さんでは、まな板に定規が仕込まれていて、刺身を切る際には明確に何センチと数値化して決めていました。油の温度、具材の分量などさまざまな作業が数値化されていたのです。
その目的は、再現性を高めることと育成の効率アップとのことでした。格段に人材の成長スピードが上がったそうです。
観察と分析の賜物です。
弊社にも独自のデザインの物差しが存在します。
トライアンドエラーを繰り返し、感覚を数値化した最適な物差しを作り上げたわけです。この物差しを使えば経験の浅いデザイナーでも見たときに美しいと思えるデザインに仕上げることができます。
ちなみにこの話は、仕事だけの話ではありません。
ゴルフをされるなら、徹底的に形式化を試みている方がいるはず。
動画見て研究してるでしょ。
クラブ選びのとき計測してるでしょ。
打ちっぱなしで自分のスイングの動画撮ってるじゃ~ん。
その目的は再現性を高めるためですよね。
まさに同じですね!(笑

相手の話をちゃんと聴けていますか?
他者とのコミュニケーションを今一度見直そう
相手の話を聴くとは
- ほめる
- 相手の意見を頭から否定しない
- 耳を傾けて聴く
- 相手の意見を引き出す質問力
など。
このような基本的なコミュニケーションができていなければノウハウコミュニケーション®は成り立ちません。仕組みも働きません。
ここの部分は動画で解説していますので、ぜひ参照してください。
特に質問力については、練習して身につけていただきたいと思います。
ノウハウコミュニケーション®
ノウハウコミュニケーション®の種類
代表的なノウハウコミュニケーション®を4つあげます。
1
2
3
4
いずれも、人対人の間でのやりとりですが、口頭だけでなく、何かしらの媒体を通してのやりとりとなっています。DXが進む昨今ではデジタルツールを介してのノウハウコミュニケーション®も多く存在し、誰かの頭の中にしか存在しないノウハウではコミュニケーションをとることも難しくなっていっています。
つまり、ノウハウの明文化を後回しにするということは組織の将来を左右すると言っても過言ではないとということになります。
ノウハウコミュニケーション®がなければ、仕組みは意味をなさない。
逆も然りで、
仕組みがなければ、ノウハウコミュニケーション®は成り立たない。
ここまで読んでいただいた方には想像が容易いのではないかと思います。
仕組みを整える目的の多くは、
- 業務標準化
- 属人化の脱却
- 業務効率化
- 人材の教育
- 理念やミッションの業務への落とし込み
すべて、ノウハウの明文化が必要であり、明文化されたノウハウを譲渡する、伝える、ボトムアップ、共有する行為(ノウハウコミュニケーション®)が必要不可決です。
仕組みを整えるためには様々な取り組みが必要になるため何から手をつければいいのやらと悩まれるかと思いますが、答えは一択です。
ノウハウの明文化から始めましょう。
形式知の明文化から始められると良いかもしれません。
そして伝えるやボトムアップなどのノウハウコミュニケーション®を促してみましょう。
難しく考えず、簡単なところから始める。
その方が愉しめます。
慣れてきたら、暗黙知の形式化にチャレンジしてみましょう。